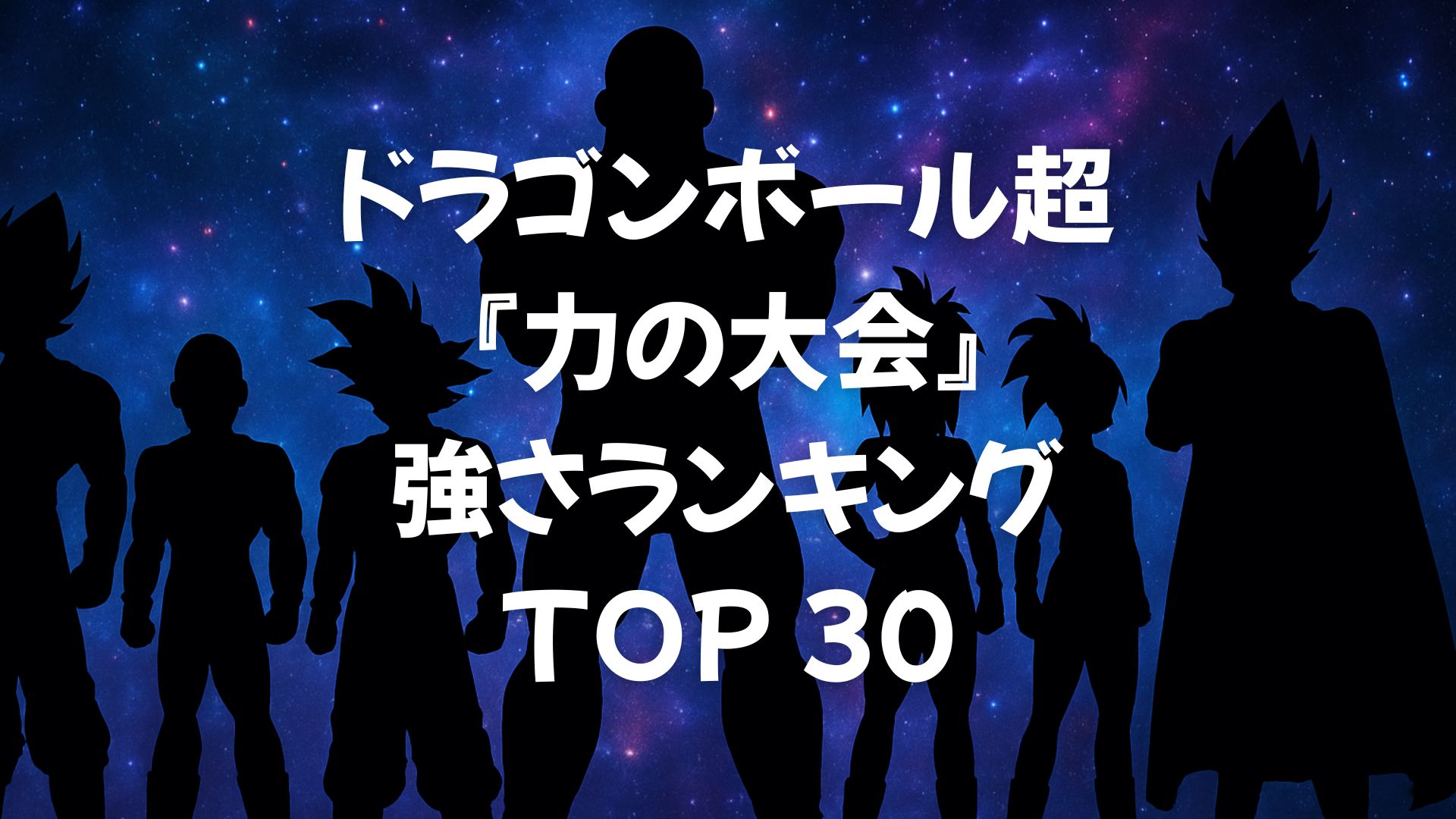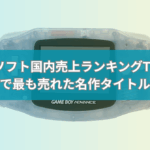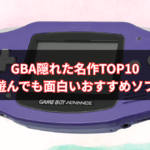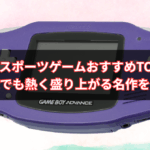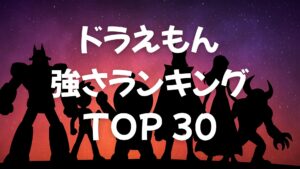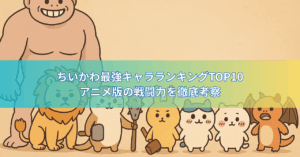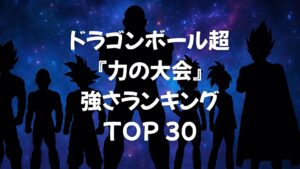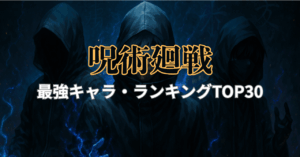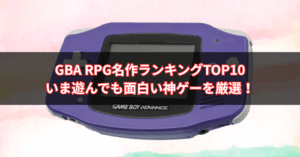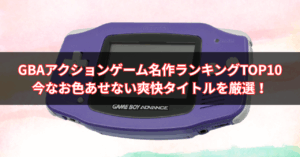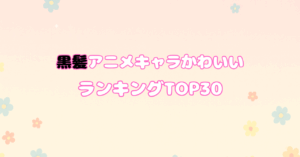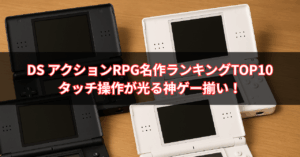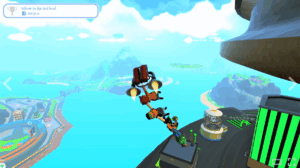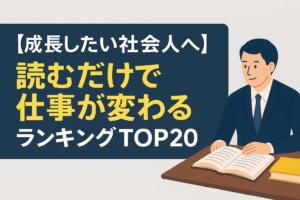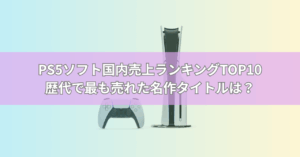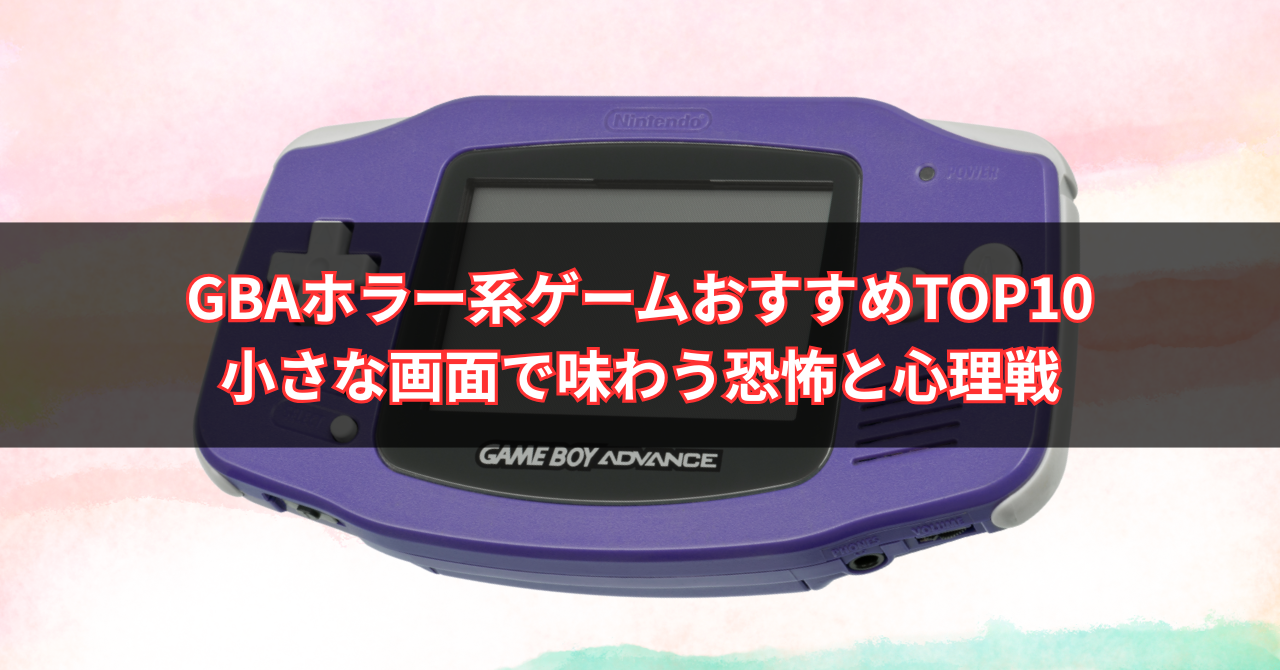
GBA時代、ホラーやサスペンスといえば据え置き機の独壇場と思われがちですが、
実はアドバンスにも“静かに怖い”“不気味に引き込まれる”名作が多数存在しました。
小さな画面に閉じ込められた恐怖は、むしろ想像力を刺激し、
プレイヤーの記憶に深く残るそんな「携帯機ホラー黄金期」の作品たちを厳選。
本記事では、GBA専用タイトルの中からホラー・サスペンス要素を強く持つおすすめ10本を紹介します。
そこまでこわくないよ!
第1位:リヴィエラ ~約束の地リヴィエラ~
(2002年/スティング)
死後の世界を舞台にしたファンタジーRPG。
明るいビジュアルの裏に、輪廻・死神・自己犠牲といった重いテーマを抱えています。
静かなBGMと、淡々と進む演出が心理的ホラーに近い没入感を与え、
GBAの「沈黙の恐怖」を象徴する1作です。
第2位:真・女神転生 デビルチルドレン ~光の書/闇の書~
(2003年/アトラス)
子ども向けRPGの皮をかぶったダークファンタジー。
“悪魔と契約”“人間の罪”といったテーマを正面から描き、宗教的な不気味さが漂います。
終盤の展開は倫理的にも重く、「子供用メガテン」の名を超えた精神的サスペンスとして評価されています。
第3位:サモンナイト クラフトソード物語
(2003年/バンプレスト)
明るい外見のアクションRPGながら、ストーリーは精霊との契約・裏切り・喪失など、
心理的な葛藤が中心。
会話劇のテンポや人物の動機描写が深く、
“表は友情、裏は倫理と孤独”という二面性がサスペンス的な緊張を作ります。
第4位:LUNAR LEGEND(ルナ・レジェンド)
(2002年/ゲームアーツ)
GBA版として再構築された『ルナ』は、オリジナルとは異なりやや重い演出が際立ちます。
人間の裏切り、運命の暴走、記憶喪失などを主軸にしたストーリーが、
純愛と破滅を行き来する幻想サスペンスRPGへと変化。
第5位:ナポレオン
(2001年/任天堂)
史実ベースの戦略ゲームですが、
霧に包まれた戦場、悪霊軍の襲撃、仲間の消失など、
超常現象的な演出が多く、不気味な戦記ファンタジーに仕上がっています。
BGMも静かで不穏。じわじわと緊張が高まる異色タイトル。
第6位:シャイニングソウルII
(2003年/セガ)
シリーズの中でも特に「闇」「腐敗」「廃墟」をテーマにしたアートが目立つ。
GBAのドット表現で描かれる墓地・洞窟・荒廃都市は、
まるでファンタジーに潜むデスサスペンスのような雰囲気を醸します。
戦闘と探索の合間に漂う静寂が印象的。
第7位:ボクらの太陽
(2003年/コナミ)
太陽光を利用して吸血鬼を倒す“実験的ホラーアクション”。
カートリッジに光センサーを内蔵しており、実際に太陽光を集めて戦うという斬新な仕組み。
物語は吸血鬼伝説×終末世界で、BGMもどこか不気味。
「明るさ=命」「暗闇=死」という概念を体感できる唯一無二のホラー体験。
第8位:ボクらの太陽 続・ボクらの太陽 ~太陽少年ジャンゴ~
(2004年/コナミ)
前作より物語がシリアス化し、死者の魂や“闇の太陽”など、
よりダークなテーマに踏み込んだ続編。
吸血鬼との因縁や、太陽の失われた世界という舞台が、
終末的ホラーサスペンスを感じさせます。
第9位:ミスタードリラー2
(2001年/ナムコ)
カラフルな外見に反して、
酸素切れや圧死といった“死と隣り合わせのパズル性”が恐怖を生む。
地底の静けさとプレイヤーの焦燥感が組み合わさり、
精神的サスペンスとしての緊張感が光る隠れた名作。
第10位:ロックマンエグゼ4.5 リアルオペレーション
(2004年/カプコン)
プレイヤーがAIナビの管理者として現実時間で交流する異色作。
人工知能の自我やシステム異常、時間連動イベントなど、
テクノロジー系サスペンスの先駆け的存在。
明るいシリーズの中で最も“静かな恐怖”を感じる一本。
GBAホラー・サスペンス系ゲームおすすめTOP10一覧表
| 順位 | タイトル | 発売年 | メーカー | 特徴 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | リヴィエラ ~約束の地リヴィエラ~ | 2002年 | スティング | 死と輪廻を描く心理ホラーRPG。 |
| 2 | 真・女神転生 デビルチルドレン 光の書/闇の書 | 2003年 | アトラス | 宗教的テーマが不気味なダーク作品。 |
| 3 | サモンナイト クラフトソード物語 | 2003年 | バンプレスト | 精霊契約をめぐる心理サスペンスRPG。 |
| 4 | LUNAR LEGEND | 2002年 | ゲームアーツ | 幻想的で悲劇的なサスペンスファンタジー。 |
| 5 | ナポレオン | 2001年 | 任天堂 | 静寂と霧が支配する不気味な戦場劇。 |
| 6 | シャイニングソウルII | 2003年 | セガ | 廃墟探索が恐怖を呼ぶダークアクション。 |
| 7 | ボクらの太陽 | 2003年 | コナミ | 太陽光センサーを活かした吸血鬼ホラー。 |
| 8 | 続・ボクらの太陽 ~太陽少年ジャンゴ~ | 2004年 | コナミ | 闇と死をテーマにした終末的続編。 |
| 9 | ミスタードリラー2 | 2001年 | ナムコ | 酸欠の恐怖を描く心理的パズル。 |
| 10 | ロックマンエグゼ4.5 リアルオペレーション | 2004年 | カプコン | AIと現実を結ぶテクノロジーサスペンス。 |
まとめ
GBAというハードは、今振り返ると「明るい携帯機」という印象が強いかもしれません。
しかし、その裏側では、
音・静寂・ドットの影・淡い演出といった、派手さとは真逆の要素を活かして、
“プレイヤーの想像力に訴えるホラー”を実現していました。
『ボクらの太陽』シリーズは、太陽光センサーという実験的な仕掛けを用い、
「光」と「闇」という対立構造を物理的に感じさせたホラー体験でした。
ホラーゲームなのに日中プレイを推奨するという発想は、まさにGBA世代特有の逆転アイデアです。
一方で、『リヴィエラ』や『真・女神転生 デビルチルドレン』のように、
精神性・死生観・宗教観を物語に落とし込む作品も登場しました。
これらはビジュアルで驚かせる“恐怖”ではなく、
人間の内面を静かにえぐる心理的ホラーであり、携帯機という密閉された環境にこそ相性が良かったと言えます。
また、『ナポレオン』や『シャイニングソウルII』のような一見ファンタジー/戦略系の作品にも、
GBA特有の“沈黙の間”や“画面の暗さ”を利用した演出が見られます。
これがプレイヤーの想像力を刺激し、「何かが潜んでいる感覚」を生み出していたのです。
つまり、GBAのホラー/サスペンス作品群は、
「携帯機でも恐怖を成立させられる」ことを実証した先駆的存在でした。
派手な3D表現や高音質サウンドに頼らず、
“少ない情報の中で怖さを作る”=想像させる恐怖を武器にしていたのです。
現在では、これらの作品はレトロゲームの域を越えて、
「携帯ホラーの原型」として再評価されています。
Switch Onlineなどで一部タイトルが復刻されたことで、
改めてGBAという時代の“静かに怖い世界”が再び脚光を浴びています。